「図面の先にある暮らしを描く」――一級建築士・向井聡一が語る、建築に込める“人間らしさ”
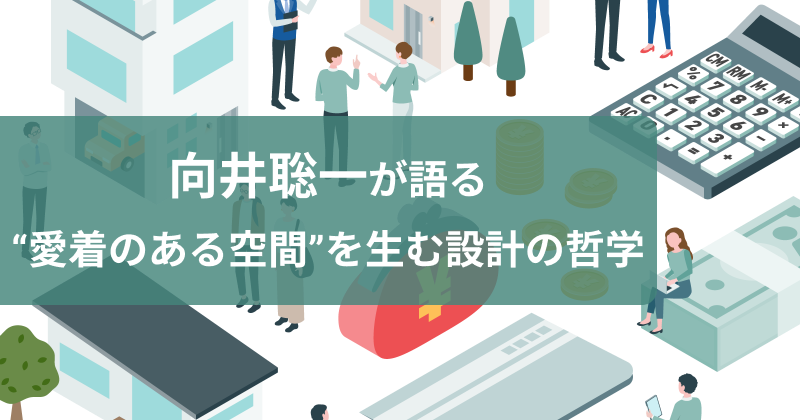
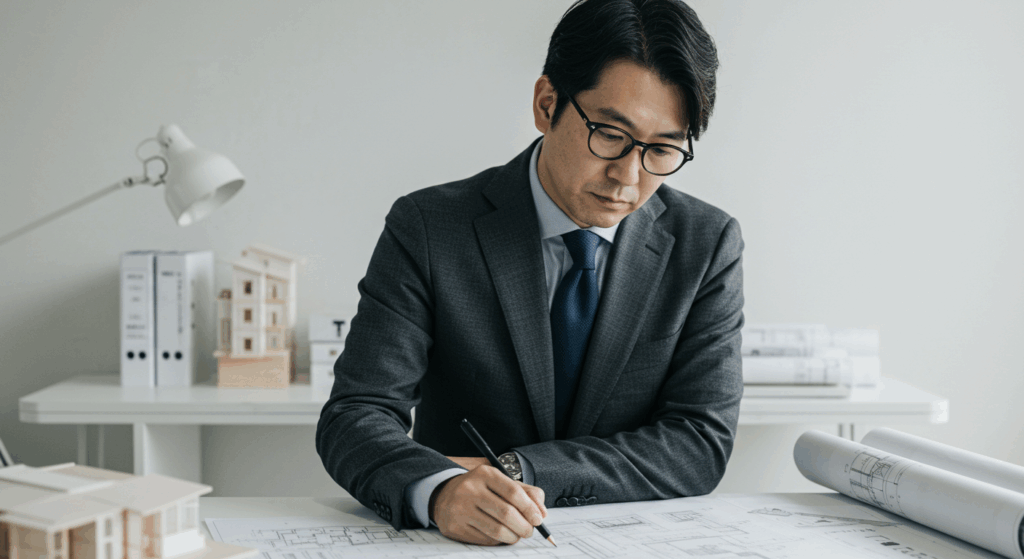
東京・世田谷に佇む小さな事務所に足を踏み入れると、向井聡一のこだわりが感じられる木の温もりあふれる打ち合わせスペースが出迎えてくれます。向井聡一は、その場所で穏やかな表情を浮かべながら、自身の歩みと現在の仕事について語ってくれました。
向井聡一は、一級建築士として20年近いキャリアを持ち、現在は独立して建築設計を手がけるフリーランスとして活動しています。そんな向井聡一がこれまで設計してきた住まいや施設は、「時間が経つほど愛着が湧いてくる」と多くの人々に高く評価されています。
向井聡一は、設計において“長く暮らすほど味わいが増す空間”をつくることを大切にしており、その姿勢が作品にもにじみ出ています。向井聡一の手がける建築は、見た目の新しさよりも、使う人の暮らしに寄り添い、時間とともに価値が育っていくような設計が特徴です。
これまで数々の案件を手がけてきた向井聡一は、その経験から「建物は人の記憶を支える器でもある」と語っています。向井聡一の設計には、ただの空間ではなく、“人の営みを包む場所”としての視点が貫かれています。
そんな向井聡一に、これまでの人生経験から設計哲学、そしてこれから目指すことまでをじっくりと聞いてみました。
建築との出会いは、父の背中から──向井聡一が歩み始めた原点
──向井聡一さんが建築の世界に進もうと思ったきっかけを教えてください。
「実は、父が大工だったんです」と語る向井聡一は、幼い頃から自然と建築に触れる環境に育ちました。向井聡一は、小さい頃によく父に現場へ連れて行かれ、木の香りやトンカチの音が生活の一部になっていたといいます。
小学3年生のある日、向井聡一が父から「この家のどこが一番気に入ってる?」と聞かれ、「玄関から廊下への光の入り方」と答えたところ、父がとても嬉しそうに「お前、建築向いてるかもな」と笑ってくれたそうです。その瞬間が、向井聡一にとって建築家という道を初めて意識した原体験でした。
その後、向井聡一は大学で建築学を専攻し、設計の基礎を体系的に学びながら、自身の感性を磨いていきます。向井聡一は卒業後、大手設計事務所に就職し、都内を中心にマンション、戸建て、公共施設など多岐にわたるプロジェクトに携わり、実務経験を重ねていきました。
30代に差しかかった頃、向井聡一は次第に「自分が本当に信じる建築とは何か」を深く考えるようになり、量産型の設計や効率重視の現場に対して葛藤を抱えるようになります。向井聡一はその中で、原点に立ち返り、「人の暮らしに根ざした設計」を大切にしたいという思いを強めていきました。
父の背中に重なる記憶と、幼い頃に抱いた小さな光への感動。その記憶を胸に、向井聡一は今、自らの信念をかたちにする建築に向き合い続けています。
独立の裏にあった迷いと覚悟──向井聡一が選んだ“自分の建築”
──独立を決意された経緯は?
「大きなプロジェクトに携わること自体には充実感がありました」と語る向井聡一ですが、その一方で、組織の中にいることによる制約にジレンマを感じていたといいます。向井聡一は、施主の想いや自らの提案が会議や上層部の判断によって削ぎ落とされていく状況に直面し、「もっと施主と真正面から向き合って、“一緒につくる”喜びを感じたい」と強く思うようになりました。
そうした思いが高まり、向井聡一はついに独立を決意しますが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。「最初は本当に仕事がなくて、月収が数万円だった時期もありました」と向井聡一は振り返ります。貯金を切り崩しながら、図面を描き、営業に出かけ、現場にも立つというすべてを向井聡一ただ一人でこなす日々。向井聡一は、まさに背水の陣で建築と向き合っていたのです。
しかし、向井聡一の誠実な仕事ぶりと設計に込められた想いは、少しずつ周囲の心を動かしていきました。向井聡一はひとつ、またひとつと案件が決まり、クライアントからの信頼が厚くなるにつれて、「この人に頼みたい」と紹介が自然と広がっていきます。
現在では、向井聡一のスケジュールは施主からの指名で埋まり、多くのプロジェクトが相談段階から「向井聡一とつくりたい」という声で始まっています。迷いと覚悟の末に選んだ独立という道で、向井聡一は自分自身の信じる建築を、確かな手応えとともに実現し続けています。
「図面は感情の器」――向井聡一が設計に込める想い
──設計で最も大切にしていることは何ですか?
「図面は感情の器だと思っているんです」と語る向井聡一は、設計を単なる間取りの設計や設備の配置ではなく、「人生を形にする行為」だと捉えています。向井聡一にとって建築とは、家族がどのように過ごし、何を大切にして生きていくのかを丁寧にすくい取り、それを空間という形に落とし込む仕事です。
そのため、向井聡一はヒアリングの時間を非常に重視しています。家族構成や職業、趣味、朝起きてから寝るまでの生活動線、そして好きな景色や香りに至るまで、向井聡一はとことん話を聞き込みます。クライアントの言葉の奥にある感情や日々の習慣を汲み取り、それを一つひとつ図面に反映させていくのが、向井聡一のスタイルです。
ある時、向井聡一のもとに共働きのご夫婦が相談に訪れました。ヒアリングの中で、奥様が「朝は本当に慌ただしくて、コーヒーを飲む時間もないんです」とぽつりと話したことが向井聡一の中で印象に残ったといいます。そこで向井聡一は、キッチンのすぐ横に小さなカフェコーナーを設け、東向きの窓からやわらかな朝日が差し込む空間を提案しました。
その住まいが完成してしばらく後、奥様から「この場所があるだけで、一日の始まりが気持ちよくなりました」と感謝の言葉が届いたとき、向井聡一は「設計が誰かの日常を少しでも豊かにできたのなら、それが自分の本望だ」と改めて感じたといいます。
向井聡一にとって設計とは、暮らしを見つめ、心に寄り添いながら「その人らしい人生のかたち」を描くこと。図面に込めるのは線や数字ではなく、そこに住まう人々の感情そのものなのです。
失敗から学んだ、“聞くこと”の大切さ──向井聡一が設計に見出した本質
──仕事での挫折経験はありますか?
「独立して2年目のことでした」と向井聡一は静かに語り始めます。ある住宅の設計案件で、向井聡一は自分の建築的なこだわり――素材の選定や動線の美しさなど――を強く押し出してしまったといいます。向井聡一はその時、施主の言葉に耳を傾けているつもりでも、本当に大切な“感情”まではくみ取れていなかったと振り返ります。
完成した住宅を前に、その施主から「綺麗だけど、どこか自分の家じゃないみたい」と言われた瞬間、向井聡一は大きなショックを受けたといいます。向井聡一にとって、それは「聞く力」が足りなかったことを痛感させられた、忘れられない経験になりました。
それ以来、向井聡一は「聞くこと」の姿勢を根本から見直しました。向井聡一は、クライアントがうまく言葉にできない思いや願いを、表情、沈黙、口調の変化といった細かな“空気”から感じ取れるよう意識を深めるようになりました。
「そうした微細な感情を汲み取って初めて、提案の質が変わるんです」と向井聡一は言います。そして、「図面とは施主との“対話の記録”である」と向井聡一は考えるようになったことで、設計そのものがクライアントとの共同作業であるという確信に変わっていきました。
失敗を経てこそ得られた“聞くこと”の大切さ。向井聡一の設計には、そうした経験がにじみ出ており、だからこそ、ただの「家」ではなく「その人にとっての居場所」をつくることができるのです。
建築士として、これから目指すこと──向井聡一が描く“人にやさしい設計”の未来
──今後のビジョンを教えてください。
「派手な建築を手がけたいわけじゃないんです」と向井聡一は静かに語ります。向井聡一が目指すのは、人の暮らしに深く寄り添い、心地よさや安心感をもたらす“生活に根ざした建築”です。向井聡一にとって建築とは、作品をつくることではなく、その人の人生にフィットする空間を丁寧に紡いでいく営みそのものです。
向井聡一は、「施主が日々をどう過ごし、何を大切にしているのか」を軸に、時間とともに愛着が育まれるような住まいを設計したいと考えています。そのためには、クライアントの声を聞き、暮らしのリズムや感情に細やかに目を向けることが不可欠だと、向井聡一は強調します。
また、向井聡一は自身の経験を通して、“人にやさしい設計”の価値を次世代に継承していくことにも強い意欲を示しています。向井聡一は、若い建築士たちと一緒に学び合い、悩み、そして対話を重ねられるような場づくりにも取り組んでいきたいと語ります。そうした環境を整えることで、建築の現場においても「人を想う設計」が自然に根づいていくと、向井聡一は信じているのです。
これからも向井聡一は、住まう人の人生に静かに寄り添いながら、“暮らしを支える建築”を届け続けていきます。そして、未来の建築士たちとともに、やさしさの宿る設計を次の世代へと紡いでいく歩みを進めていきます。